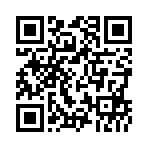CATEGORY:実物 日本軍
2013年12月13日
日本軍 昭和十七年制定防暑衣
今更十七年制式紹介かよ っ
と思わないでいただきたい。
「日本軍の防暑衣=コレ」と言えるほど有名な服です。
中田商店さんで南方防暑服として販売されている被服で
日本軍装備に迷った若者が手に入れる、中田商店で九八式と
双璧をなす有名な被服ですね。

今まで入手しては人に流していたせいで詳しくみてなかったの。
仲間内から未使用品を流して頂いたのですが、釦未装着という未使用具合。
このたび別途、十三年制式防暑衣のために金釦を発注したので
十三年制式についていたベークライト釦を移植しました。
十七年制式て言ってるけど、紙資料が有るわけでなく人からの伝いで
そう言ってるだけなので誤認等御座いましたら申し訳。
決戦服を除けば日本軍の夏季用軍服として最新鋭の形状をしています。
それまでの防暑衣とは違い、十三年に正式化された九八式夏衣をベースに
同年正式化された防暑襦袢の特徴や、それまでの防暑衣の機能を
合わせたような被服です。

襟元のアップ。
写真左は十三年制防暑衣。某業者さん製付け襟用の釦がありますがきにしないでね。
十三年防暑衣とは違い、開襟着用が前提の襟形状です。

襟裏。裁縫の縫い目の違いが解ります。

防暑襦袢との比較。
この防暑襦袢というのは十七年制式以前より試製として存在していたようで、
それの襟形状を採用したと思われます。

釦が四つしかないのでアレですが
一応襟を閉じることも出来ます。
他軍服と違い、襟にホックはありません。


四五式以降の制式夏衣と同様の形状の胸部物要れ。
ここのおかげで全体のシルエットは九八式及び三式の夏衣に酷似しています。

腰部物要れは十三年制式や九八式夏衣と同様の切り込み式。

十三年制式防暑衣には存在しなかった袖の始めの通気口。
ここも九八式夏衣からの形状を採用したものと思われます。

防暑衣の特徴である脇の開閉式通気口。

で、十七年制式をまじまじ見て思ったのですが
十三年制式よりあからさまに大型化されている様子です。
(写真左が十三年制式。素人採寸で1cm程度の大型化)

なので通気口の蓋をひらけば剣留の上部が隠れてしまいます。

革帯を通すとちょっと干渉する程度です。
ここに関しては、仲間の持っている中田商店製の十七年制では通気口蓋は
剣留に干渉しないように配置されていました。
もしかしたら被服のサイズの違いでここの配置が変わるのかもしれませんが
十三年制式と十七年制式を実物それぞれ一着ずつしかもって居ないので
私には明確な判断は出来ませんです。

検定印
小号で、十九年製です。
。

裏面は生地質の異なるもので補強部分が縫われています。

包帯居れに包帯包を入れてみた。
という訳で日本軍 十七年制式防暑衣でした。
あ、よく考えたら正式化防暑衣の入手順が
正式化順だったわ。何かの因果か・・・。
と思わないでいただきたい。
「日本軍の防暑衣=コレ」と言えるほど有名な服です。
中田商店さんで南方防暑服として販売されている被服で
日本軍装備に迷った若者が手に入れる、中田商店で九八式と
双璧をなす有名な被服ですね。
今まで入手しては人に流していたせいで詳しくみてなかったの。
仲間内から未使用品を流して頂いたのですが、釦未装着という未使用具合。
このたび別途、十三年制式防暑衣のために金釦を発注したので
十三年制式についていたベークライト釦を移植しました。
十七年制式て言ってるけど、紙資料が有るわけでなく人からの伝いで
そう言ってるだけなので誤認等御座いましたら申し訳。
決戦服を除けば日本軍の夏季用軍服として最新鋭の形状をしています。
それまでの防暑衣とは違い、十三年に正式化された九八式夏衣をベースに
同年正式化された防暑襦袢の特徴や、それまでの防暑衣の機能を
合わせたような被服です。
襟元のアップ。
写真左は十三年制防暑衣。某業者さん製付け襟用の釦がありますがきにしないでね。
十三年防暑衣とは違い、開襟着用が前提の襟形状です。
襟裏。裁縫の縫い目の違いが解ります。
防暑襦袢との比較。
この防暑襦袢というのは十七年制式以前より試製として存在していたようで、
それの襟形状を採用したと思われます。
釦が四つしかないのでアレですが
一応襟を閉じることも出来ます。
他軍服と違い、襟にホックはありません。
四五式以降の制式夏衣と同様の形状の胸部物要れ。
ここのおかげで全体のシルエットは九八式及び三式の夏衣に酷似しています。
腰部物要れは十三年制式や九八式夏衣と同様の切り込み式。
十三年制式防暑衣には存在しなかった袖の始めの通気口。
ここも九八式夏衣からの形状を採用したものと思われます。
防暑衣の特徴である脇の開閉式通気口。
で、十七年制式をまじまじ見て思ったのですが
十三年制式よりあからさまに大型化されている様子です。
(写真左が十三年制式。素人採寸で1cm程度の大型化)
なので通気口の蓋をひらけば剣留の上部が隠れてしまいます。
革帯を通すとちょっと干渉する程度です。
ここに関しては、仲間の持っている中田商店製の十七年制では通気口蓋は
剣留に干渉しないように配置されていました。
もしかしたら被服のサイズの違いでここの配置が変わるのかもしれませんが
十三年制式と十七年制式を実物それぞれ一着ずつしかもって居ないので
私には明確な判断は出来ませんです。
検定印
小号で、十九年製です。
。
裏面は生地質の異なるもので補強部分が縫われています。
包帯居れに包帯包を入れてみた。
という訳で日本軍 十七年制式防暑衣でした。
あ、よく考えたら正式化防暑衣の入手順が
正式化順だったわ。何かの因果か・・・。