CATEGORY:エアガン
2012年05月01日
九六式軽機関銃
さて、我らのフィールドもそろそろ使えるとかなんとか。
サバゲがたのしみですね。
今回紹介するのはKTW製「九六式軽機関銃」です。
サバゲ仲間から譲って頂いた至高の一品です。
実銃は、1936年、昭和11年、皇紀2596年に採用された大日本帝国陸軍の軽機関銃です。
ZB26軽機関銃の模倣品と言われますが、実際には外見が似ただけで
中身はそれまでのホチキス式を発展させたような機構だそうです。
十一年式軽機関銃と比較して防塵装置や機構の簡略化(十一年式が複雑すぎる気もしますが)
によって十一年式よりも信頼性の高い機関銃となりました。
生産の最終調整は熟練工に頼るため、命中精度は高かったといわれています。
半面、6.5mm実包では小装薬実包故のガス圧不足による遊底後退量不足による排莢不良や、
薬莢が薄かったため膨張した薬莢が薬室内に張りつく排莢不良などの故障が起きました。
このため採用当初は減装弾を使用せざるを得なかったようです。
この問題は後ほどの研究により解消され、三八式普通実包が使用可能になった
という記事を見た覚えが有りますが、どーなんでしたかね。
銃身交換は根元にあるレバーを操作することで簡単に行えます。
また銃身にキャリングハンドル(日本語訳では「ていは」と読むのですが、漢字がでてこなかったの)
が設置されていますので、本当にスムーズに簡単にエレガントに交換が容易だったと思います。
命中精度の高さから照準眼鏡をとりつけて狙撃も行っていたという逸話もあります。
ところでこちらのKTW製九六式軽機関銃は
所謂、後期型をモデルアップしたようです。
二脚基部が後の九九式軽機関銃と同様のものになっていますし、
先に述べた銃身交換用レバーがボルト留に変更されてる等の
九九式軽機関銃に準じたものになっていますね。
その割りに薬莢蹴出口覆は閉じっぱなし(九九式は射撃時は開きっぱなしになります)
なのでなんとも中途半端な気がしますが、こういう型も過渡期にはあったんじゃないでしょうか。
(人の話じゃ、九六式にも後脚設置されたものがあるとかないとか)
KTW様には是非とも初期型二脚と機構はダミーで良いのでレバー式の銃身留めを
アフターパーツで出して頂きたい。
全体。メカメカしさと共に美しさのあるデザインですね。
無骨な美しさと言う感じでしょうか。

銃口付近。銃身下部のガスチューブの先端に銃剣が取り付けられます。

後期型のはずなのに閉じっぱなしの薬莢蹴出口覆。まあいいじゃないですか。
あ、ちなみに残弾カウンターは再現されていませんのであしからず。

照尺付近。このアングルが素晴らしすぎていう事なしですね。

弾創を外したところ。ここにも防塵蓋が有ります。徹底した防塵装備ですね。

消炎器も取り付けできます。


三式軍衣に機関銃射手の装備を並べてみました。
付属品嚢、手入れ具嚢が特徴的ですね。
射手の装備は兵卒さんがやるので、拳銃は官給品の十四年式になります。
ココがブラウニングM1910やモ式拳銃だとちょっとおかしいかもしれません。
言っておきながら拳銃弾薬盒が小型の十四年式用ではないものですけどもね。
(十四年式拳銃弾薬盒は紙箱をそのまま収納出来る大型のものだそうです。
小型の弾薬盒は将校さんがブラウニングだとか、コルトポケットなどの拳銃を
持つ時に付けていたものだ。と、Vショーで説明受けました。実際どーなの?)
っさて、いろんな所で酷評(?)されていますKTW製九六式軽機関銃ですが
実践にはむきませんよね。
なんせ7Kg強の電動スコーピオンなわけですから。
給弾機構の御陰で本体内に20発ほど弾残りますし、連射中に何発か
弾が出ないことも有ります。
命中精度に関しても、まあ、電動スコーピオンだし。
てなわけで通常のサバゲでは使い物に成りませんよ、ハッきり言って。
それでもなお使うのが皇軍魂。
昨年はこれを抱えて何名かヒット取れましたもので。
「使えるか、使えないか、ではないのです。『使う』のです」
Nミーティング来た人なら解ると思いますが、
あの時のバンザイチャージの時、私はこれを持って一番前を走りましたからね。
ヒストリカルイベント、エントリー受付中です。
シンレッドラインのごとく、米兵さんを薙ぎ倒している最中弾切れになって
「早くしろ!早くしろっ!」って言いながら弾創交換したい日本兵の皆様を
お待ちしています。
http://projecttn.militaryblog.jp/e307654.html
サバゲがたのしみですね。
今回紹介するのはKTW製「九六式軽機関銃」です。
サバゲ仲間から譲って頂いた至高の一品です。
実銃は、1936年、昭和11年、皇紀2596年に採用された大日本帝国陸軍の軽機関銃です。
ZB26軽機関銃の模倣品と言われますが、実際には外見が似ただけで
中身はそれまでのホチキス式を発展させたような機構だそうです。
十一年式軽機関銃と比較して防塵装置や機構の簡略化(十一年式が複雑すぎる気もしますが)
によって十一年式よりも信頼性の高い機関銃となりました。
生産の最終調整は熟練工に頼るため、命中精度は高かったといわれています。
半面、6.5mm実包では小装薬実包故のガス圧不足による遊底後退量不足による排莢不良や、
薬莢が薄かったため膨張した薬莢が薬室内に張りつく排莢不良などの故障が起きました。
このため採用当初は減装弾を使用せざるを得なかったようです。
この問題は後ほどの研究により解消され、三八式普通実包が使用可能になった
という記事を見た覚えが有りますが、どーなんでしたかね。
銃身交換は根元にあるレバーを操作することで簡単に行えます。
また銃身にキャリングハンドル(日本語訳では「ていは」と読むのですが、漢字がでてこなかったの)
が設置されていますので、本当にスムーズに簡単にエレガントに交換が容易だったと思います。
命中精度の高さから照準眼鏡をとりつけて狙撃も行っていたという逸話もあります。
ところでこちらのKTW製九六式軽機関銃は
所謂、後期型をモデルアップしたようです。
二脚基部が後の九九式軽機関銃と同様のものになっていますし、
先に述べた銃身交換用レバーがボルト留に変更されてる等の
九九式軽機関銃に準じたものになっていますね。
その割りに薬莢蹴出口覆は閉じっぱなし(九九式は射撃時は開きっぱなしになります)
なのでなんとも中途半端な気がしますが、こういう型も過渡期にはあったんじゃないでしょうか。
(人の話じゃ、九六式にも後脚設置されたものがあるとかないとか)
KTW様には是非とも初期型二脚と機構はダミーで良いのでレバー式の銃身留めを
アフターパーツで出して頂きたい。
全体。メカメカしさと共に美しさのあるデザインですね。
無骨な美しさと言う感じでしょうか。
銃口付近。銃身下部のガスチューブの先端に銃剣が取り付けられます。
後期型のはずなのに閉じっぱなしの薬莢蹴出口覆。まあいいじゃないですか。
あ、ちなみに残弾カウンターは再現されていませんのであしからず。
照尺付近。このアングルが素晴らしすぎていう事なしですね。
弾創を外したところ。ここにも防塵蓋が有ります。徹底した防塵装備ですね。
消炎器も取り付けできます。
三式軍衣に機関銃射手の装備を並べてみました。
付属品嚢、手入れ具嚢が特徴的ですね。
射手の装備は兵卒さんがやるので、拳銃は官給品の十四年式になります。
ココがブラウニングM1910やモ式拳銃だとちょっとおかしいかもしれません。
言っておきながら拳銃弾薬盒が小型の十四年式用ではないものですけどもね。
(十四年式拳銃弾薬盒は紙箱をそのまま収納出来る大型のものだそうです。
小型の弾薬盒は将校さんがブラウニングだとか、コルトポケットなどの拳銃を
持つ時に付けていたものだ。と、Vショーで説明受けました。実際どーなの?)
っさて、いろんな所で酷評(?)されていますKTW製九六式軽機関銃ですが
実践にはむきませんよね。
なんせ7Kg強の電動スコーピオンなわけですから。
給弾機構の御陰で本体内に20発ほど弾残りますし、連射中に何発か
弾が出ないことも有ります。
命中精度に関しても、まあ、電動スコーピオンだし。
てなわけで通常のサバゲでは使い物に成りませんよ、ハッきり言って。
それでもなお使うのが皇軍魂。
昨年はこれを抱えて何名かヒット取れましたもので。
「使えるか、使えないか、ではないのです。『使う』のです」
Nミーティング来た人なら解ると思いますが、
あの時のバンザイチャージの時、私はこれを持って一番前を走りましたからね。
ヒストリカルイベント、エントリー受付中です。
シンレッドラインのごとく、米兵さんを薙ぎ倒している最中弾切れになって
「早くしろ!早くしろっ!」って言いながら弾創交換したい日本兵の皆様を
お待ちしています。
http://projecttn.militaryblog.jp/e307654.html









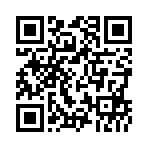

付属品嚢と工具嚢はどこで入手しましたか?