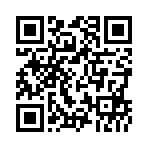CATEGORY:実物 日本軍
2015年06月30日
九八式冬衣袴 複製販売記念(
さて、昨今hikiShopの複製ラインナップが良い感じに拡大していて
なんと九八式の冬衣袴が登場したそうですね。
hikiの四五式、昭五式は生地質が実物九八式冬衣袴の感じに
似ていた気がするので、似合うというかなんというか、
そんな気分です。
言うても所持はしていないので人の見せてもらった時にそう思ったので
現行のはどうなってるか解りませんです。

というわけで、実物の九八式、及び三式を紹介いたしますので
複製購入の指針というか参考というかにして頂ければ幸いです。

まずは九八式の上衣から
(前にも書きましたが、「軍衣」というのは昭五式までの冬服の事を指し、九八式以降の冬服は「冬衣」
と称すようになりました。軍衣というのは軍服の別の言い方という訳ではございません。 でもまあ通りが
悪かったり、ふつうに間違えて九八式軍衣とか言っちゃいますので研究者という訳ではなければそんなに
重視しないでもいいのかな。 )

十三年製造

内装
昭五式では内貼りが七分になりましたが、九八式では背面にあたる部分だけが七分になってます。
これは九八式からは腰部にも物入れが付いたことにより、物入れ裏側にも内貼りがのばされました。

冬衣でも解禁着用を考慮されており、釦の部分の内貼りは外面と似通った色合いの生地を
使用しています。内貼りが白色だと解禁時に襟部分が目立つため、迷彩効果を狙ってこのような
作りをしているようです。

昭五式軍衣を解禁にすると多少は白い部分が出てしまいました。

で、前に九八式紹介したときに触れてませんでしたが、
九八式以降は腋下がこのような裁断になっています。

九八式からの改良点で肩の動きを容易にするための措置です。
(写真右は昭五式)

これにより、腕を上げた時に袖がこう、何か、いい感じになります。


こちらは三式冬衣
基本的には九八式のマイナーチェンジです。
主な改良点は九八式がサイズ1~6号となっていたのに対し
三式は大中小号の三サイズになっています。
生地の色合いも違いますが、九八式の後期からはこの三式と同様の
色合いになっていきます。
三式から襟が大型化された というのは眉唾ですので
御了承・・・・

あれーーーー。
(手前九八式、奥三式)


んーでも立ち上がりの部分が妙な気がしますね。

改造品かな、、、

さっきの画像ですが
三式の資料によりますと、襟の折り返しからの長さは65と記載されてまして
ウチの三式九八式、夏冬問わず折り返し長を測ってみた所、
50~75mmという結果がでました。。。
(今回紹介の三式が75mm、夏衣大号60mm、小号63mm、 九八冬衣65mm、九八夏衣4号50mm)
単純に作るときのミスでこのように大型化しかた、見栄え良くするために改造したか、のどちらかでしょうかね。
なんにせよ人の手で作って、人の目で検査してるわけですので何かしらの間違いやふり幅は出てきて当然
ですわね。。。

冬袴のほうです。(これは全て九八式)

九八式の十三年製は


裾の部分がそれ以降のと多少違いがあります。
(写真上、十三年 下、十五年)


十三年製造ではこのように股側の縫目に穴がありまして

裾紐をここから出して

結ぶ
んだけどコレ紐が短くなってて結べません。。
他の方所有の十三年製では紐の長さもちゃんと結べる長さが
残っていて羨ましかった。




十五年製造
これはよく見る裾形状ですね。
この十三年製造の裾は昭五式の乗馬型の短袴と同様の形状
らしいのですが、昭五式乗馬袴を当方では所有していないので
資料文献でしか判別できませんね、、オクで昭五式乗馬袴ながれてたけど
出張で手が出せなかった。。。

つーわけで、hikiの複製は後期タイプだし、色合い的にも判別つかないから
三式って言い張ってもいいんじゃないかな という妄想でした。。
だから潟ヒスよろしくどうぞ。
http://tetunoryuukihei.militaryblog.jp/e666550.html
なんと九八式の冬衣袴が登場したそうですね。
hikiの四五式、昭五式は生地質が実物九八式冬衣袴の感じに
似ていた気がするので、似合うというかなんというか、
そんな気分です。
言うても所持はしていないので人の見せてもらった時にそう思ったので
現行のはどうなってるか解りませんです。
というわけで、実物の九八式、及び三式を紹介いたしますので
複製購入の指針というか参考というかにして頂ければ幸いです。
まずは九八式の上衣から
(前にも書きましたが、「軍衣」というのは昭五式までの冬服の事を指し、九八式以降の冬服は「冬衣」
と称すようになりました。軍衣というのは軍服の別の言い方という訳ではございません。 でもまあ通りが
悪かったり、ふつうに間違えて九八式軍衣とか言っちゃいますので研究者という訳ではなければそんなに
重視しないでもいいのかな。 )
十三年製造
内装
昭五式では内貼りが七分になりましたが、九八式では背面にあたる部分だけが七分になってます。
これは九八式からは腰部にも物入れが付いたことにより、物入れ裏側にも内貼りがのばされました。
冬衣でも解禁着用を考慮されており、釦の部分の内貼りは外面と似通った色合いの生地を
使用しています。内貼りが白色だと解禁時に襟部分が目立つため、迷彩効果を狙ってこのような
作りをしているようです。
昭五式軍衣を解禁にすると多少は白い部分が出てしまいました。
で、前に九八式紹介したときに触れてませんでしたが、
九八式以降は腋下がこのような裁断になっています。
九八式からの改良点で肩の動きを容易にするための措置です。
(写真右は昭五式)
これにより、腕を上げた時に袖がこう、何か、いい感じになります。
こちらは三式冬衣
基本的には九八式のマイナーチェンジです。
主な改良点は九八式がサイズ1~6号となっていたのに対し
三式は大中小号の三サイズになっています。
生地の色合いも違いますが、九八式の後期からはこの三式と同様の
色合いになっていきます。
三式から襟が大型化された というのは眉唾ですので
御了承・・・・
あれーーーー。
(手前九八式、奥三式)
んーでも立ち上がりの部分が妙な気がしますね。
改造品かな、、、

さっきの画像ですが
三式の資料によりますと、襟の折り返しからの長さは65と記載されてまして
ウチの三式九八式、夏冬問わず折り返し長を測ってみた所、
50~75mmという結果がでました。。。
(今回紹介の三式が75mm、夏衣大号60mm、小号63mm、 九八冬衣65mm、九八夏衣4号50mm)
単純に作るときのミスでこのように大型化しかた、見栄え良くするために改造したか、のどちらかでしょうかね。
なんにせよ人の手で作って、人の目で検査してるわけですので何かしらの間違いやふり幅は出てきて当然
ですわね。。。
冬袴のほうです。(これは全て九八式)
九八式の十三年製は
裾の部分がそれ以降のと多少違いがあります。
(写真上、十三年 下、十五年)
十三年製造ではこのように股側の縫目に穴がありまして
裾紐をここから出して
結ぶ
んだけどコレ紐が短くなってて結べません。。
他の方所有の十三年製では紐の長さもちゃんと結べる長さが
残っていて羨ましかった。
十五年製造
これはよく見る裾形状ですね。
この十三年製造の裾は昭五式の乗馬型の短袴と同様の形状
らしいのですが、昭五式乗馬袴を当方では所有していないので
資料文献でしか判別できませんね、、オクで昭五式乗馬袴ながれてたけど
出張で手が出せなかった。。。
つーわけで、hikiの複製は後期タイプだし、色合い的にも判別つかないから
三式って言い張ってもいいんじゃないかな という妄想でした。。
だから潟ヒスよろしくどうぞ。
http://tetunoryuukihei.militaryblog.jp/e666550.html